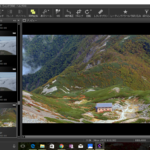登山で撮影。山岳写真でよく使うレンズの焦点距離

登山をする時はなるべく荷物を軽くしたいですね。登山で軽量化は正義です。荷物が重ければ遭難リスクも高まります。本格的な登山に耐えうる体が出来ていない人は(私も含めて・・・)余分なものを持たずになるべく荷物を軽くすべきでしょう。
でもせっかく山に行くのでいい写真が撮りたい、と思うのは心情。なので、なるべく持参するレンズを絞りたいですね。
どんなレンズを持って行くのがよいかというのは以前に書いて、便利ズームが手軽でいいねという話をしたのですが、
やっぱり、画質にこだわりたい。という人もたくさんいらっしゃると思います。そんな方なら必要な焦点距離をカバーできる写りのよいレンズを持って行く事になると思います。
目次
登山で使った焦点距離
私が登山でどの焦点距離で撮影しているのかを調べてみました。
標準ズームレンズのみ持参の時
6月に登った甲斐駒ケ岳では、18-55mmズームレンズのみでしたがここで使った焦点距離は
| 焦点距離 | 撮影枚数 | 現像枚数 |
| 18-24mm | 208枚 | 11枚 |
| 24-35mm | 69枚 | 8枚 |
| 35-55mm | 74枚 | 4枚 |
ワイド側が圧倒的に使用数が多いですが、ほとんどが記録用写真でした。実際に現像したものは比率で言えば24-35mmの標準画角が多いようでした。
複数のレンズを持参した時
4月に登った御坂山塊西側(王岳、節刀ヶ岳等)では、8-16mmズーム、35mm単焦点、55-200mmズームを持って行きました。使った焦点距離は
| 焦点距離 | 撮影枚数 | 現像枚数 |
| 8-16mm | 310枚 | 10枚 |
| 35mm | 251枚 | 5枚 |
| 55mm | 5枚 | 1枚 |
| ~200mm | 60枚 | 5枚 |
山行中は35mm単焦点。撮影地に着いてからレンズ交換のスタイル。もともと超広角で富士山とその裾野を撮りに行ったので、必然的に8-16mmが多くなっております。55mmは甲斐駒ケ岳ではテレ端の焦点距離でしたが、こちらでは望遠レンズのワイ端なので比較できるように別に拾ってみました。
風景写真で長めの焦点距離はあまり使っていないですね。やはり風景を切り取る範囲が狭いので、山の高いところで見られる壮大な風景を撮るという使い方はしませんので利用回数が限定されます。
ピンポイントを切り取りたい時や、野生動物を取るときは必要になりますが、風景主体であればあまり必要性がないと感じております。
どんな風に撮りたいかで焦点距離は決まってくるので、山に登る前に撮りたい風景のイメージを膨らませておくことが大事ですね。
私がズームレンズを使うときは、目に留まった風景について、どうして気になったのかをちょっと考えてから、主題を定めて焦点距離を決めるようにしております。
ですので、ファインダーを覗きながらズームを調整するということはなるべくしないようにしています。これは画角の感覚を養う訓練も兼ねてそうしているのですが、このようにした方がどんな写真が撮りたいか、どんな写真になるのかを頭でイメージしやすくなると思っております。
焦点距離別撮影用途
どんな風に撮りたいかを考えるときに選ぶ焦点距離を自分なりにまとめてみました。
8mm〜16mm(35mm換算12mm〜24mm)
いわゆる超広角と言われる焦点距離です。この焦点距離で撮影するときは、壮大な景色をダイナミックに撮りたい時に使います。
広い範囲が写ることが魅力の焦点距離ですが、実はそれよりも魅力的というか私が好きなのは、強烈なパースペクティブがつけられるところです。
中央に向かってクワッと伸びる遠近感がたまらないですね。
また、このくらいの焦点距離のレンズは被写体に寄れますので、前景にグッと寄って撮ると奥に向かって広がるダイナミックな写真が撮れます。
超広角すごく楽しいです。

8mm(換算12mm)の作例 羊蹄山山頂からの風景
でも、適当に撮るとなにを撮っているのかわからなくなるので、自分が何を主題に取りたいのかよく考えて使う必要があります。超広角が難しいと言われている所以ですね。
この画角で撮る時に私が持っていくレンズはこれです。
 |
シグマ 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM ニコン用 【店頭受取対応商品】 価格:59,880円 |
![]()
18mm〜35mm(35mm換算28mm〜52.5mm)
この焦点距離は非常に使い勝手がよい焦点距離です。
特に、18mm(35mm換算28mm)は個人的な感覚で言うと、目だけを動かして前の景色を眺めるような画角になるので、記録写真を撮るのには最適な焦点距離だと思っています。
RICOHのGRのような単焦点のコンデジや多くのスマホもこのくらいの焦点距離を採用しているので、やはり一番使いやすいのだと思います。
18mm(35mm換算28mm)の画角でも結構パースペクティブつきますし、超広角のような周辺部の歪みも目立ちにくくなるので、風景撮りにも大活躍します。
見たままの広大な景色を納めたいと言う時によい焦点距離だと思っています。
一方、35mm(35mm換算52.5mm)は前の景色を目を動かさないで眺める感じに近い画角だと思っております。
見た目と最も近い感覚で撮れ、歪みも少ないので見たままに前に撮りたい時に使う焦点距離です。写した写真と見た感じが同じなのですが、ファインダーを覗くと意外と狭い感じもするので、人間が認知する画角は意外と狭いものなんだなと感じる焦点距離です。

28mm(換算42mm)の作例 羊蹄山外輪
標準ズームレンズはキットレンズしか持っていないのですが、シグマの17-70mmが焦点距離もいいところをカバーできていて、写りもよいので欲しいですね。
 |
《新品》 SIGMA(シグマ) C 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM(ニコン用)[ Lens | 交換レンズ ]【KK9N0D18P】 価格:32,320円 |
2019.3.21追記 現在標準ズームレンズにTAMRON 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2(A032)を使っています。
将来的にフルサイズに移行できるようA032を現在は使用しております。画角がフルサイズ換算36-105mmとなり、広角側が狭くなりますが不自由を感じるシチュエーションは少なめです。むしろ望遠端が長くなりそちらのメリットの方が大きく感じております。どうしても広角が必要な時はSIGMA8-16mmを使っております。A032気になるところもありますが、とっても気に入っています。
こちらのA032関連記事もどうぞ
50mm~55mm(35mm換算75mm~82.5 mm)
55mm(35mm換算82.5mm)あたりは被写体を見つめた時のような画角の焦点距離になります。割合ピンポイントなところを周りの風景も入れて撮りたい時に使う焦点距離です。
個人的にはこの焦点距離が超広角と共にお気に入りで、迫力のある風景を切り取るのに非常にいいと思っております。主題を明確にしやすい画角でもあると思います。
しかし、この焦点距離は結構画角が狭いので、もし単焦点レンズでこれだけ持っていくと結構撮りづらい場面が多いかと思います。
でも、単焦点で固定された焦点距離で撮りたいものを撮るにはどう表現するかということをするのも楽しいです。登山の場合、脚を使って風景を切り取るというのがなかなかできない場合が多いので、単焦点レンズだと大変ですがその分解像感の高い写真が撮れますし、多くはF値が1.4や1.8等明るいレンズが多いので、ボケも楽しめます。単焦点レンズで登山もストイックで楽しいです。

55mm(換算82.5mm)作例 登山者を阻む岩稜
この焦点距離で最近よく使っているレンズはAi Micro-Nikkor 55mm F2.8Sです。
大昔の古いレンズですが、現在でも販売されております。
古いのにビックリするくらい解像するレンズです。ハーフマクロレンズですが、私の使い方では十分寄れますし遠景もすごく綺麗に撮れます。マニュアルフォーカスですが、風景撮りならば特に不便を感じることはないでしょう。

Ai micro-nikkor 55mm F2.8S で寄ってみました
中古で玉数が多いので、安く売っているのを見かけたら使ってみることをお勧めします。価格は状態でだいぶん違いますが、並の中古で15000円前後、悪いもので10000円前後。程度の良いもので20000円前後でしょうか。
 |
【あす楽】 【中古】 《良品》 Nikon Ai Micro-Nikkor 55mm F2.8S [ Lens | 交換レンズ ] 価格:22,800円 |
 望遠の画角
望遠の画角
被写体が遠くて標準ズームレベルの焦点距離では撮れない時や、小さいところをピンポイントで切り取りたい時に使用します。
焦点距離が長くなると前景や背景のボケも出し易く楽しめます。
登山での風景を撮るのではあまり使う機会がないのですが、いざという時にあるといい時があるので、私の場合余裕があればAF-S DX Nikkor 55-200mmを持っていきます。このレンズは安い割にはシャープによく写り、胴沈式なのでかなりコンパクトかつ軽量です。AFは遅いですが風景撮りには問題ないです。
 |
ニコン AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II 価格:35,980円 |
![]()
個人的には、画質にこだわるなら28mmと55mm(35mm換算42mmと82.5mm)の単焦点を持って行きます。超広角や望遠も持って行くければそれに越したことはないですが、この2本があればまあまあ撮れるかなと思います。
なるべく楽に登って満足できる写真を撮りたいですね。では。